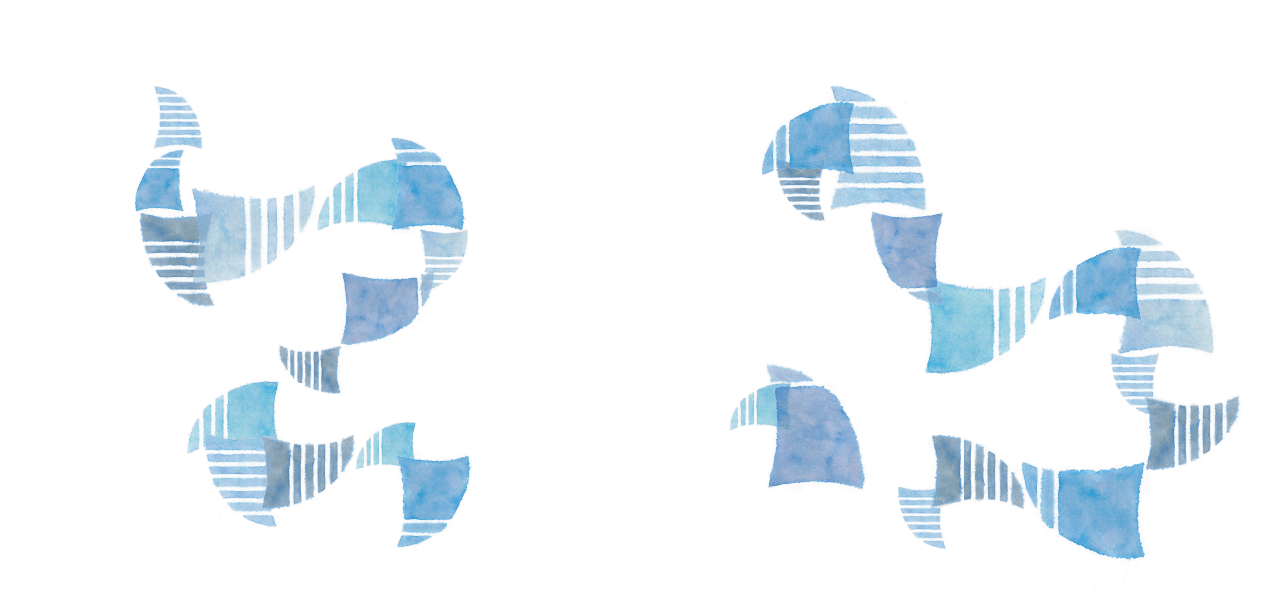中・高生時代について
「お前はオレみたいになるな」
国語 / 横倉 浩一

Q1 先生は中学生・高校生時代はどんな生徒でしたか。
中学で野球部、高校でラグビー部に入っていて、運動するのはわりと好きな生徒でした。
野球部時代はピッチャーでした。諸事情あってチームに投手は私しかいませんでした。いつも楽しそうにみんなでワイワイやってる野手たちを横目に、ほぼ一人で別メニューの練習を日々こなしていました。いつも孤独を感じていました。
自分の投手としての信条は、「絶対にフォアボールを出さない」ということでした。投げる球は直球か「とくに曲がるというわけでもない遅い球」だけでしたが、その遅~い球を使ってバッターを手玉にとるのが好きで(まぁ、性格は悪かったわけです)、スローボールをわりと多投するタイプの投手でした。あと、ヒット打って喜んでる走者を獣のように素早い動作でピシャッと牽制球アウトにするのも得意でした(まぁ、性格は悪かったわけです)。
印象に残っているのは延長12回裏まで0対0で進んでサヨナラ負けを喫した中学最後の試合です。終わりの方では握力がほとんど無くなって今まで出さなかった四球も出し、球も遅い球「しか」投げられなくなってさすがに打たれて負けました。マウンドのすぐ横をゆっくり抜けていく(自分にはスローモーションのように見えた)サヨナラヒットの軌跡がまだ記憶に残っています。
また、試合が終わったあと寄り道した駄菓子屋でチームメイトから、
「ヨコ(横倉)がずっと0点で抑えてくれたのに俺たちが最後まで1点も取れなくてゴメン」
と言われた時、「オレのせいで負けた」とばかりと思っていた自分の中に何かしら熱い感情がこみ上げたのも覚えています。
「思ってたほどオレは孤独じゃなかったんだな」
そう気づかされた瞬間でした。
また、教室では休み時間に何人かで集まっては演劇の「エチュード」(即興劇。むろん当時そんな言葉は知りませんでしたが)のようなことをして盛り上がっていたのを覚えています。まぁ、多分「ちょっと変な連中だな」と思われていたグループの一員だったわけです。
「刑事と犯人の取り調べシーン」や「誘拐犯が身代金を要求するシーン」等をその場でアドリブで作ってみたり、地球外生命体に卵を産み付けられた宇宙船乗り組み員が船内に戻ったあと急にもがき出し、その腹から奇怪な生物が飛び出る、みたいな映画のワンシーン(『エイリアン』)をあーだこーだ言いながら再現してみたり、そんな、まったく何の意味も無いことに熱中しては仲間内でゲラゲラ笑い合うのが至福の時間でした。
面白いものに触れた時、ただそれを「見ている」だけではもの足りなくて、自分で「やってみる」ことまでしたくなる、そういう気質が強かったのかもしれません。私にも、あるいは当時私の周りにいた友達にも。
Q2 先生の中学校・高校時代の今に繋がる思い出を教えてください。
現在、公私とも本を読むことを中心とした生活を送っている私ですが、読書という習慣が自分の人生で始まったのはハッキリ「中学1年の夏」だと断定できます。
私は小3くらいから中3までの間、夏休みになると2週間くらい母親の実家である福島の農家で過ごしていました。そこで私の「子守り役」だったのが4歳くらい年上の従兄・トシオ兄でした。基本的に農家の子は夏休み中、家の手伝いをするのが当たり前だったので、とうぜん私もその作業に参加することになりました。仕事は芋を掘ったり、わらで縄を作ったり、肥料を畑にまいたりと、今思えばすこぶる地味な作業ばかりだったのですが、都会で育った私には、そのどれもが新鮮で、めちゃくちゃ面白かったのを覚えています。また、そんなめちゃくちゃ面白い農作業を大人と同じく完璧にこなすトシオ兄は私の憧れでした。
また一方でトシオ兄は典型的な田舎の「不良」(当時はそういう言い方をしました)でもありました。煙草を吸い、額には鋭い「剃り込み」が入り、髪は短めのいわゆるチリチリパーマだった年もありました。どこかから電話がかかってくる。木刀をもってバイクで出かける。夜中にアザだらけキズだらけで帰って来る。そんなことも滞在中たびたびありました。でも当時の私はトシオ兄のそんな側面さえもかっこいいと感じていました。
「お前はオレみたいになるな」
何がきっかけでそういう話になったのかよく覚えていませんが、中一の夏休み、高校生くらいだったトシオ兄が私に言いました。
「オレはケンカばっかして勉強もせず本も読まなかったから、ろくな人間になれない」
今思うと高校生がこんなことを言うか、とも思うのですが、とにかく実際そう言ったのだから仕方ありません。トシオ兄がその時どんな状況にあり、心にどんな深い絶望をかかえていたのか、今となっては想像することすらできません。
「だから、せめてお前は本を読め」
自分にとってのヒーローから言われて、私の「本を読まない人生」はハッキリ終わりました。
その翌日だったか、トシオ兄と私はバイクで二人乗りして町に一軒だけある本屋に向かいました。本屋の前に来るとトシオ兄は言いました。
「オレは読んだことがないからどんな本がいいか分からない。これをやるから自分で選べ」
そう言って千円札を二枚渡してきました。「読んだことない」のはこちらも同じだったので、迷いに迷ったあげく、名作っぽい本(井上靖の本)と娯楽っぽい本(推理もの?)の二冊を二千円ちょうどくらいで買いました。
「え?二冊買ったの?お釣りは?」
「ないです」
その時トシオ兄の顔に一瞬イラッとした表情がきざしましたが、それはとにかく、この日から私の人生に読書という要素が加わり、53歳になった現在までそれを中心とした生活がずっと続いているのです。

国語 / 横倉 浩一